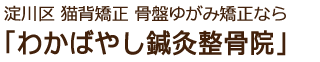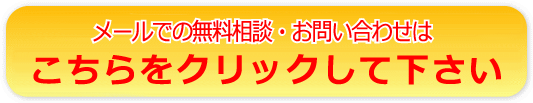寝違いはなぜ起きるのか?|知られざる原因と身体のメカニズム 塚本の整骨院
## 寝違いはなぜ起きるのか?|知られざる原因と身体のメカニズム
朝起きた瞬間、「あれ?首が動かない…」
そんな寝違いは、実はただの“寝姿勢の問題”ではありません。
寝違いの多くは、**日常生活の中で溜まった筋肉・関節・神経へのストレスが、睡眠中に限界を超えた結果**として起こります。
つまり、「寝ている間に急に痛めた」のではなく、**すでに首や肩が限界の状態にあった**ということなのです。
—
### 🔹原因①:首・肩まわりの筋肉疲労と血流不足
デスクワークやスマホ操作が多い現代人は、
無意識のうちに「うつむき姿勢」を続けています。
この姿勢では首の後ろや肩の筋肉が常に引っ張られ、血流が悪くなります。
その結果、筋肉の中に疲労物質がたまり、硬く・冷たく・酸素不足の状態に。
そのまま寝てしまうと、
寝返りなどのわずかな動きでも筋肉が伸びきらず、
「ピキッ」と小さな損傷を起こしてしまうのです。
これが寝違いの痛みの正体です。
—
### 🔹原因②:睡眠中の姿勢と寝具の影響
「枕が合わない」「同じ姿勢で寝てしまう」なども、寝違いの大きな要因です。
首は本来、S字カーブを描くように支えられることでリラックスしますが、
枕が高すぎたり低すぎたりすると、首に無理な角度がつき、
筋肉や関節に負担をかけてしまいます。
また、仰向けやうつ伏せで長時間同じ姿勢を取ることで、
筋肉が一方向に引っ張られ、血流が滞ります。
その状態で寝返りを打つと、筋肉がついていけず炎症を起こすのです。
—
### 🔹原因③:肩甲骨や背骨の歪み
首の動きは実は「首だけ」で行われているわけではありません。
肩甲骨や背骨、胸郭(胸の骨の動き)など全体が連動しています。
そのため、姿勢の悪さや骨格の歪みがあると、
首に過剰な負担が集中し、結果的に寝違いが起こりやすくなります。
特に猫背や巻き肩の人は、
首が前に出る「ストレートネック」状態になっており、
寝違いを繰り返す傾向があります。
—
### 🔹原因④:ストレス・自律神経の乱れ
意外に見落とされがちなのが、**ストレスによる自律神経の乱れ**です。
ストレスが強くなると交感神経が優位になり、
筋肉が常に緊張して硬くなります。
この状態で寝ても筋肉がリラックスできず、
わずかな寝返りで筋肉が「ブチッ」と引きつれることがあります。
また、自律神経の乱れは血流を悪くするため、
首や肩に酸素が届きにくく、回復が遅れてしまうのです。
—
### 🔹原因⑤:冷えや天候の変化
冷房の風が首に当たったり、気温差が大きい季節にも寝違いは起きやすくなります。
筋肉は冷えると硬くなり、血流が悪化。
その状態で朝方の冷え込みや寝返りが加わると、筋肉がついていけず痛みが出ます。
特に秋冬や梅雨の時期は、気圧の変化によって筋肉や神経が敏感になり、
「また寝違えた…」という方が増える傾向があります。
—
## 寝違いは“突然ではなく、積み重ねで起こる”
つまり、寝違いは偶然ではなく、
**日々の姿勢・生活習慣・ストレスの積み重ねが引き金**となって起きるものです。
ですから、
・湿布で一時的に痛みを抑えるだけ
・マッサージでその場しのぎ
では再発を防ぐことはできません。
根本的な原因である「筋肉の硬さ」「姿勢の歪み」「自律神経の乱れ」を整えることで、
寝違いを“起こさない身体”にしていくことが大切です。